相続人の調査
そのためには、相続人は誰なのか、何人いるのかをキチンと調査し、法的に証明する必要があります。
そのために、被相続人(亡くなられた方)の出生時から死亡時までの戸籍謄本を集めて、調査するようになります。

仮に被相続人が昭和10年生まれだとすると、その当時からの戸籍謄本が必要になりますので、調査には専門知識が必要になります。
そこで、当事務所では、相続手続に必要な戸籍収集を一括して代行します。
また調査した戸籍を元に、相続関係説明図を作成し、相続関係が一目で分かるようにします。
相続人調査について
戸籍調査が必要です
相続人は誰なのか、何人いるのかをキチンと把握するために戸籍調査を行ないます。
現在の戸籍謄本だけでは、過去の婚姻関係や親子関係が分からない場合があります。
そのため被相続人(亡くなられた方)の出生時まで遡って戸籍謄本を集めて調査します。
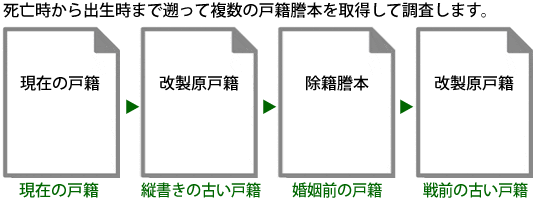
仮に被相続人が昭和10年生まれだとすると、その当時から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
そのため戸籍調査には専門知識が必要になります。
相続関係説明図とは?
戸籍調査で確認した相続関係を元に、相続関係説明図を作成します。
この相続関係説明図が不動産や銀行預金などの名義書換の際に必要となります。
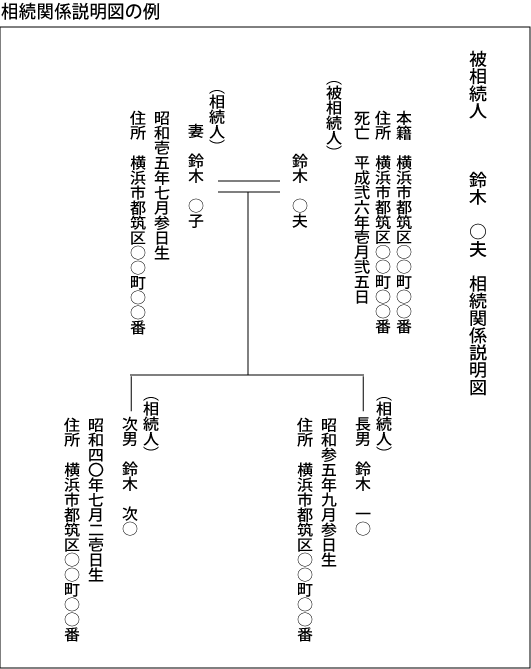
仮に被相続人が昭和10年生まれだとすると、その当時から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
そのため戸籍調査には専門知識が必要になります。
相続人とは
誰が相続人になるの?
誰が相続人になるかは、民法で決められています。
まず、配偶者がいる場合は常に相続人となります。
それ以外の相続人については、次の順位で相続人になります。
第1順位 子供
子供が既に亡くなっていて子供がいる場合は、その子供(孫)が相続人になります。(代襲相続)
配偶者がいる場合は、配偶者1/2、子供全体で1/2が法定相続分となります。
第2順位 父母
第一順位の相続人がいない場合に相続人となります。
配偶者がいる場合は、配偶者2/3、父母全体で1/3が法定相続分となります。
第3順位 兄弟関係
第一順位、第二順位の相続人がいない場合に相続人となります。
兄弟姉妹が既に亡くなっていて子供がいる場合は、その子供(甥・姪)が相続人になります。(代襲相続)
配偶者がいる場合は、配偶者3/4、兄弟姉妹全体で1/4が法定相続分となります。
相続分はどんな割合?
各相続人の相続分についても、民法で定められています。
これを法定相続分といいます。
法定相続分は、誰が相続人かで変わってきます。
民法で定められた法定相続分
順位 | 相続人 | 相続割合 |
| 第1順位 | 子供・配偶者 | 子供:1/2 配偶者:1/2 |
| 第2順位 | 父母・配偶者 | 父母:1/3 配偶者:2/3 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹・配偶者 | 兄弟姉妹:1/4 配偶者:3/4 |
遺産分割をすることで、法定相続分と異なる相続をすることも可能です。
(例えば、相続人の中の一人が全てを相続する等)
相続する財産には何が含まれるの?
相続財産には、下記のものが含まれます。
- 土地・建物などの不動産
- 現金・預貯金
- 株式など有価証券
- 貸付金・売掛金などの債権
また
- 住宅ローン
- 銀行からの借入金などの借金
などマイナスの財産も相続する財産です。
相続のお悩みに無料(初回60分)でお答えします!
045-532-5125
9:30〜18:00(月曜定休)
土曜・日曜・夜間も予約可能です。
まずは、お気軽にご相談ください。

